聞き手:和泉 潔教授(研究科長特別補佐、広報室長)
―神経のネットワークを測るインターフェイスで新たな痛み治療へ―
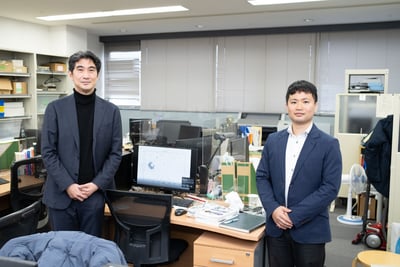
医学と工学をつないで医療をよりよくする「医工連携」という研究が広がっています。神経の働きを電子デバイスを使って直接調べることで、これまでの医療では対応が難しかった痛みなど、ヒトを苦しめる症状に立ち向かうことが可能になってきています。東京大学大学院工学系研究科の若手研究者がその成果と未来、発展について語る対談の第15回。和泉 潔教授が精密工学専攻 神経工学研究室の榛葉 健太助教と、神経工学についてインタビューします。
榛葉:「神経工学」は、脳のことを知りたい、神経のことを知りたい場合に、工学の技術を使っていこうという分野です。かなり幅広い分野なのですが、中でも私は脳の細胞ひとつひとつがどのような働きをして、結果として私たちが持つ記憶や体を動かす機能が成り立っているかということを解き明かす研究をしています。
私たちはマウスやヒトのiPS 細胞から作った神経細胞をお皿の中で培養する方法を研究していまして、培養した神経細胞を数百~数千個ほどの活動を同時に計測します。これによって、細胞一個一個がどのような活動しているか、さらに集団にまとまるとどのような活動のパターンや機能を持っているのか、ということがわかります。
和泉:脳細胞の集団としての機能が解明されることによって、どのような応用が考えられるのでしょうか? 痛みの制御などにつながりますか?
榛葉:私自身が今目指しているのは、痛みが、どのように体のどの部位で発生しているか、メカニズムを突き止めることです。これが分かると、和泉先生のおっしゃるとおり痛みを抑える方法につながってきます。
痛みに苦しんでいる患者さんはたくさんいますから、副作用の少ない、そして痛みをより効率的に抑えられるような方法の開発につながるとよいと思っています。
和泉:私自身も腰の痛みを抱えていますので、人ごとではないですね。現在は、体に痛みがあると痛み止めの薬を飲むわけですが、脳神経から痛みのメカニズムを解明できるようになると、どのようなメリットが出てくるのでしょうか?
榛葉:現在の鎮痛薬の基本的な仕組みは、痛みを感じさせる物質を作らないように抑えるというものです。残念ながら、この仕組みでは効く場合と効かない場合があるのですね。
効く場合というのは、痛みを感じさせる物質が実際に作られている場合です。一方で、長い間痛みを感じ続けると、体に本当は痛みの信号が来ていないにも関わらず、脳で一種の痛みの幻想が発生してしまうことがあるのです。すると、一般的な鎮痛剤が効かなくなってしまいます。そうした状況でも、神経の機能に介入することで痛みの発生を抑えられるようなことができると思っています。
和泉:脳から来る痛みで苦しんでらっしゃる方患者さんは多いのでしょうか?
榛葉:脊髄損傷を発症された後は、高い割合でそうした症状が現れるということが知られています。脊髄はもともと体の痛みを中継するような場所なのですが、脊髄の神経回路が変わってしまい、痛みが増幅されてしまったり、体に触っただけの信号が痛みとして送られてしまったり、ということが起きます。
和泉:そうした臨床に近い領域ですと、医学の分野とのコラボレーションが必要になりますね。
榛葉:私は基礎の細胞のレベルを研究していて、先日採択された日本医療研究開発機構(AMED)のプロジェクトなどで医学の先生と協力を進めているところです。
神経を測る技術の急速な進歩
和泉:すでに「医工連携」を進めて研究されているわけですね。将来は医学と工学の連携がこれから進んで、治療ということが薬だけではなく何らかのデバイスやチップで治療するということになっていくのでしょうか? そうした、人間の生体に関わるような情報処理デバイスの領域では、今後5~10 年でブレイクスルーやどんなことが起きると考えられますか? ブレインヒューマンインターフェースや機器を人間に埋め込む技術など、大きな発展がありそうですね。榛葉:はい。実際にヒトへデバイスを埋め込み、文字を認識したといった報告が毎年のように出てきていて、文字入力ひとつとっても精度やスピードはどんどん向上しています。以前は一文字を入力するのに10 秒、 20 秒とかかっていたものが、もう人が話すにスピードに近づいてきていて、この領域は着実に進歩しているところだと思います。
ただ、健常な人にデバイスを埋め込むというのはまだかなり難しいことですから、埋め込まない(非侵襲的)に信号を測りつつ、精度も上げていく方向で、今かなり競い合っていますね。デバイスそのものも、またそのソフトウェアの面も改良されてきています。もう少し使いやすい、精度の高いインターフェイスができてくると面白いと思いますね。
和泉:なるほど。非侵襲で脳の動きを知るようなデバイス技術はとても難しいと思っていたのですが、この部分こそ年々進歩しているわけですね。
榛葉:埋め込みデバイスで得られる信号はすごいので、最先端の研究の部分ではそうした方式をとることも多いのですが、脳波を測るといった埋め込まない方法も総じて進歩してきていますね。
和泉:病気の治療への応用にも進んできているわけですね。国内外のメーカーが商品化につなげるとすると、これから10 年でどのような製品が出てくる可能性があると考えられますか?そしてどのような背景があってそうした進歩につながったのでしょうか?
榛葉:つい最近製品化された例では、小さなチップの上で細胞を培養する製品があります。理化学研究所にいた人たちが5年ほど前にスイスで創業したベンチャー企業の製品です。従来の製品は1つのお皿の中に数10点ほどの電極があって、その周囲の細胞の活動を測るというもので、扱える細胞の数は100~200個ほどでした。それが新しい製品では、2mm×4mmほどのサイズに2万6000 点もの電極が入っていて、数千個もの細胞の活動を測ることができます。価格も、従来の製品とほとんど同じで、かなり安くなっています。これからさらに電極が増えていって、もっと使いやすいものが出てくると思います。
和泉:それはできることも段違いに多くなりますね。
榛葉:以前は細胞そのものの活動を測るだけだったところが、細胞本体だけでなく神経細胞が細胞の本体から伸ばしている「軸索」という腕でネットワークを作る様子まで追跡できるようになってきました。軸索の部分を信号がどう流れていくかというところまで、かなり詳細に調べられます。これまでは、「細胞Aが活動するとBも活動する確率が高い」というように確率で考えていたものが、実際に信号がどこをどう流れているか、というところまで見えるので、計測や解析の精度が上がっています。病気を信号から直接評価できて、適応できる場所がかなり広がっていますね。
和泉:計測技術が上がることで、病気や脳の活動の不具合まで、対応できる対象が段違いに増えるわけですね。
榛葉:はい、適用範囲が広がっていますね。今では製薬会社がこうしたしくみをかなり導入していて、新薬の候補となる化合物を探すことに使っています。創薬の開発失敗につながる大きな原因に中枢神経で副作用が出るケースがあるのですが、その副作用を予測するのにこうしたデバイスを使うと創薬のプロセスをかなり短縮できるのです。
和泉:なるほど。創薬に情報処理技術を活かせると副作用を予測できるわけですね。それは非常に大きな効果ですね。
榛葉:従来はマウスでそうしたデータを集めていたのですが、ヒトとラットやマウスではどうしても持っているタンパク質に違いがあって、ヒトと動物の種差を考えなければなりませんでした。ヒトの iPS 細胞を使うことができるようになり、さらにヒトの細胞を培養して薬を使用できるようになることで、ラットやマウスでは予測できなかった副作用がわかるようになってきたわけですね。
さらに、神経の回路網とその相互作用を調べるという面でも、研究室のお皿の中で末梢神経から脊髄につながる回路網を作ることができます。それも1種類だけではなく、2種類、3種類の細胞のネットワークを別々に培養して結合を持たせることもできるのです。すると、末梢神経の細胞を刺激すると脊髄に情報が送られる様子を模擬する、といったことができるようになります。こうした技術も並行して発達してきていますね。

生き物への興味からヒトの研究へ
和泉:大変重要だと思います。榛葉先生の研究されている技術は未来につながっているわけですね。そもそも、榛葉先生がこの方向に進もうと思われたきっかけはどんなところにあるのでしょうか?
榛葉:もともと私は静岡の自然が豊かなところの出身でして、虫や生きものを飼い、自然と触れて育ってきたのがベースにあると思います。学部生で研究室に配属されたところからかなり自由に自分のやりたいことをやらせてもらって、細胞への興味が出てきました。それがこの道に進んだきっかけかなと思います。
その上で、私は細胞を扱いつつ、工学部でもありますので、細胞の活動を計るチップを作ったり、細胞の形や神経回路のネットワークの形を制御したりするような、小さなスケールのものづくりに進んできています。
和泉: ここの研究室に来る学生さんも、榛葉先生のように生物に興味を持っていたのでしょうか?
榛葉:生物に詳しい学生は、実はそこまで多くはないのです。ただ、生物に興味があって機械を扱いたい、というモチベーションを持つ学生が、40人のクラスがあったら中に数人程度はいまして、そこから志望してきてくれます。
精密工学科にはいくつかの柱があって、医工連携や生体への応用もそのひとつです。ですから精密工学科に来る時点で、元々生体に興味があるとはいえます。その上で、研究室によって医療用ロボットのような比較的大きなスケールのものから、細胞のように小さなところまで分かれていきますね。
和泉:生体と工学を結ぶ境界領域に興味を持つ学生さんが、入ってからより詳しく生物学を学んでいかれるわけですね。それでは、高校生で生体にも工学にも興味あるという学生さんに向けて、勉強をしたほうが良いことがあったら教えてください。
榛葉:まずは、自分が面白いと思えることを大事にして、その周辺の勉強を進めていくと良いと思います。高校から大学に入って勉強をしていくと、興味というのはどんどん変わっていきます。それは健全なことだと思いますし、あまりこだわりすぎずにさまざまなことを試してみて、そのときに面白いと思ったことに飛び込んで、ちょっと頑張ってみる。そこからだんだんとつきつめてみると良いのではないかと思います。
和泉:自由に興味関心を持ったところを追求できる環境が大事というわけですね。榛葉先生にもそうした、興味が移り変わってきた経験があったりするのでしょうか?
榛葉:実は、私は剣道を小学生から高校、大学でも続けていまして、どちらかというと剣道を頑張っていた学生時代だったのです。そこから気づいたら研究に没頭していました。
そうしたところから「体を動かすのが好きだから、体を動かす神経の細胞を知りたい」という関心や、物を作りたい、細胞の働きを知りたい、という興味につながることもあります。学生にもできるだけ一人ひとりの興味に合わせてテーマを設定して、多少は失敗してもいいからやってみようという方向が良いのではと思いますね。
和泉:工学のことも、生体のことも多く学ばなくてはいけない場合、興味を持つ分野だから挑戦できるわけですね。
榛葉:はい、勉強することが多いので、興味を持てないと嫌になってしまいます。「これが面白そうだな」というそのモチベーションが重要だと思っています。
和泉:榛葉先生の5年、10年の未来への目標を教えてください。
榛葉:はい。今は、痛みの回路網の全貌を解明することを目指しています。体の末梢で痛みが発生して、その痛みが脊髄を伝わって脳に届く。それぞれの場所でどのような不具合が起きることで、痛みがより強く脳で感じられてしまうのか、本来存在しない痛みが脳に伝わってしまう現象は細胞のレベルでどのようになっているのか、詳細に解明したいと思っています。
将来は、現在ではなぜ痛みが発生するのかわからないけれど、痛みがあるという患者さんにとって、どのような理由で痛みが発生しているのかまで分かるようになり、その上で副作用なしに痛みを効率的に抑える治療につながればよいと思っています。
Profile
榛葉 健太助教
牧之原市立榛原中学校(静岡県)出身、静岡県立榛原高等学校(静岡県)出身
聞き手 研究科長特別補佐 和泉 潔教授
私立麻布中学校(東京都)出身、私立麻布高等学校(東京都)出身
※所属や職位の情報は全て取材時点での内容です。
おすすめ記事
本件に関連する記事はこちら
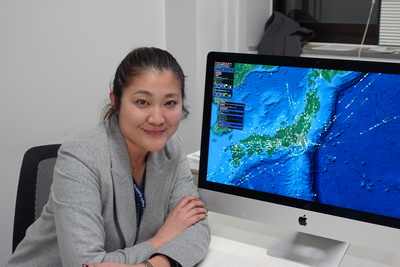
【第7回 インタビュー】航空宇宙工学専攻 伊藤 恵理先生
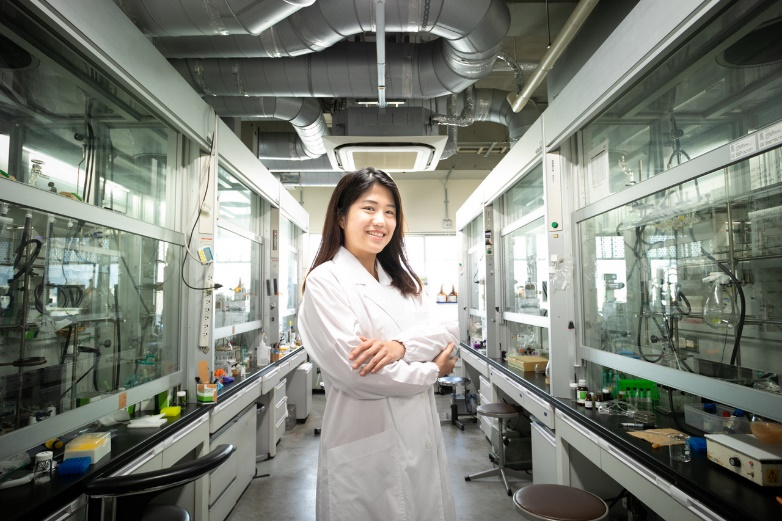
【第16回 インタビュー】応用化学専攻 西島 杏実先生


