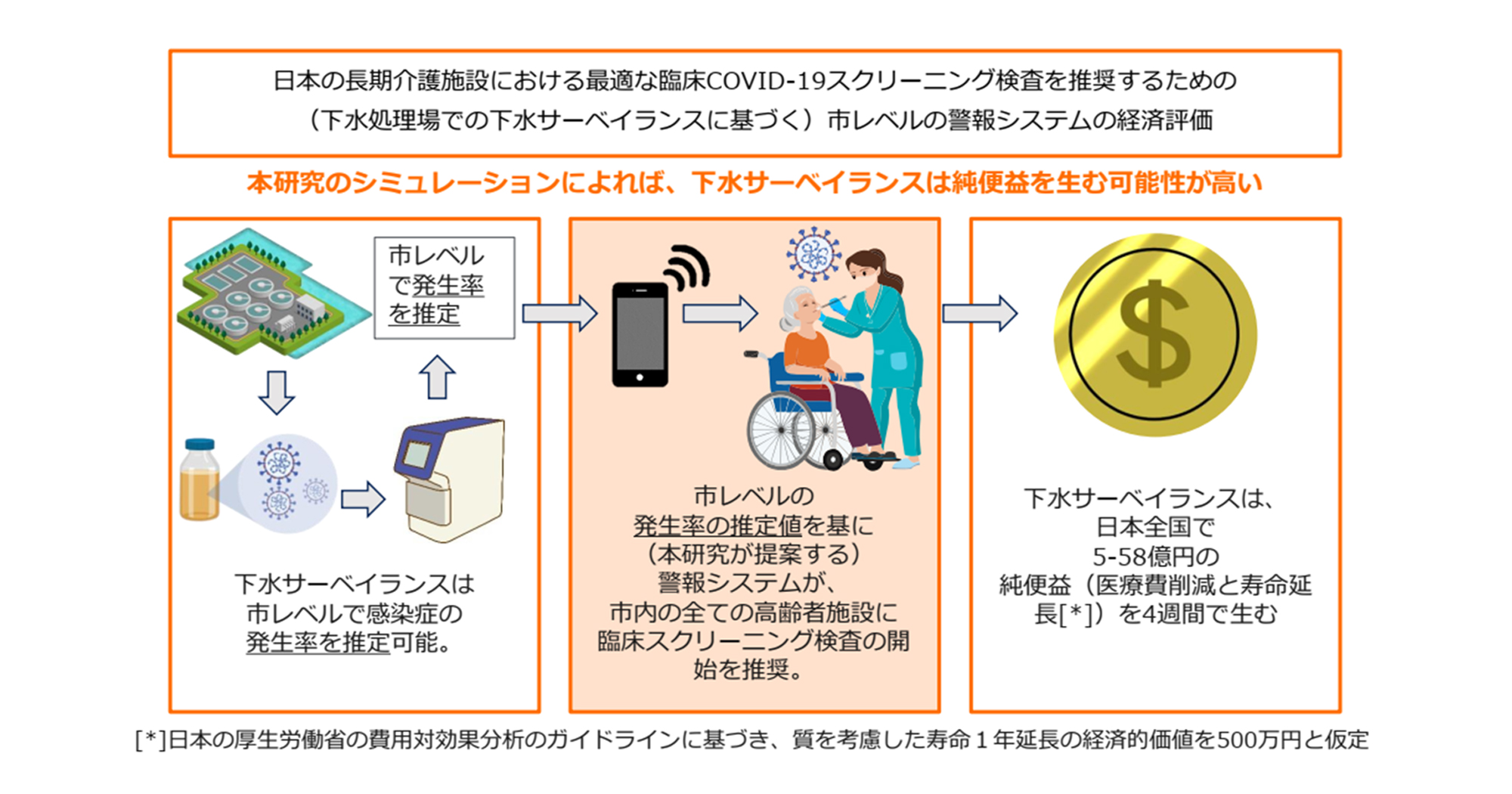発表のポイント
◆ 札幌市の都市下水中の新型コロナウイルス濃度と市内12病院の新規感染者数の関連を解析。
◆ 病院の所在する地域単独よりも都市全体の下水のウイルス濃度の方が感染者数と高い相関を示すことを明らかにした。
◆ 公開の都市下水データを利用することで、医療機関内の感染者数を推定することが可能となる。
 5類移行が下水中新型コロナウイルス濃度と病院内感染者数の相関に与えた影響
5類移行が下水中新型コロナウイルス濃度と病院内感染者数の相関に与えた影響
概要
東京大学大学院工学系研究科の北島正章特任教授、北海道大学病院感染制御部の石黒信久部長と鏡圭介薬剤師、札幌市下水道河川局などの研究グループは、COVID-19の5類移行前後いずれの時期についても、札幌市の都市下水中の新型コロナウイルス濃度が市内の12病院で確認されるCOVID-19陽性者数と高い相関を示すことを明らかにしました。
先行研究では、病院排水中のウイルス濃度と院内感染患者数との間に相関があることが報告されていました。一方、本研究の成果は、医療機関が自施設の排水を検査せずとも自治体等により公開される都市下水のデータを活用することで医療機関のCOVID-19症例数を推定可能であることを示すものです。さらに、都市下水中のウイルス濃度データは、今後医療機関内のCOVID-19感染制御対策の有効性を検証する上で役立つことが期待されます。
本成果は、2025年2月20日に「Environment International」でオンライン公開されました。
発表内容
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、感染者数の全数把握から定点把握への切り替えに加え、COVID-19関連の医療費の公費負担から個人の健康保険適用への変更、濃厚接触者への移動制限の撤廃、イベント開催制限の解除、飲食店の営業時間短縮要請の廃止など複数の変更が実施されました。COVID-19による死亡率は基礎疾患を持つ患者や高齢者で高く、多くの入院患者は基礎疾患を抱えているため、院内感染から守ることが重要です。下水疫学調査(注1)は臨床検査の実施状況や医療機関の受診行動に影響されることなく地域におけるSARS-CoV-2の流行動向の把握が可能であり、社会における活用の動きが進んでいます。本研究グループは以前、5類移行前(2021年2月15日~2023年2月26日)における都市下水中のSARS-CoV-2 RNA濃度が、北海道大学病院のCOVID-19症例数の推移とよく対応していたことを報告しました(関連情報:プレスリリース①)。
本研究では、上記の5類移行前の期間に加え、5類移行後(2023年5月8日~2023年10月1日)における札幌市内の5箇所の下水処理施設の流入下水(注2)中のウイルスRNA濃度(コピー/L)をEPISENS-S法(注3)(関連情報:プレスリリース②)により測定(同市ウェブサイト上で「下水サーベイランス(注4)」として公開)するとともに、同時期の市内12病院における新型コロナウイルス感染者数(人/週)のデータを取得しました。
市内12の病院における13,812件のCOVID-19症例(外来患者、入院患者、医療従事者)を分析した結果、都市下水中SARS-CoV-2濃度と週間新規感染者数は連動して推移しており(図1)、これらの間に強い相関関係があることが明らかになりました。さらに、COVID-19患者を医療従事者、外来患者、入院患者(非院内感染、院内感染)の属性に分類して解析した結果、5類移行後では医療従事者、外来患者、および非院内感染入院患者の症例数は5類移行前に比べて有意に減少しました(図2)。また、病院が所在する地域の下水中のSARS-CoV-2 RNA濃度よりも、市全体の下水中のSARS-CoV-2 RNA濃度の方が、病院のCOVID-19患者数との相関が強いことも分かりました。この相関の違いは、5類移行後においてより顕著でした。5類移行後においては、より広い下水集水域が地域全体のCOVID-19感染動向を捉えるのに効果的である可能性があります。言い換えれば、エンデミック期においては、市の下水疫学データが病院のCOVID-19患者数を反映していると考えられます。そのため、自施設の下水中のSARS-CoV-2を直接監視していない医療機関であっても、公開されている都市の下水データを利用することで、病院内のCOVID-19患者数を推定することが可能であると言えます。

図1:札幌市内12病院のCOVID-19患者数と同市の都市下水中新型コロナウイルス濃度の推移

図2:札幌市内12病院のCOVID-19患者数と同じ週の下水中新型コロナウイルス濃度の相関
〇関連情報:
プレスリリース①(北海道大学)「下水中の新型コロナウイルス濃度が医療機関における感染者数の指標になることを証明~医療機関の負荷をリアルタイムに推定するためのツールとしての下水疫学データの活用に期待~」(2023/7/27)
https://www.hokudai.ac.jp/news/2023/07/post-1274.html
プレスリリース②(北海道大学・塩野義製薬)「普及に適した下水中新型コロナウイルスの高感度検出技術(EPISENS-S法)を開発~本技術の普及による下水疫学調査の社会実装の加速に期待〜」(2022/8/8)
https://www.hokudai.ac.jp/news/2022/08/episens-s.html
発表者・研究者情報
北海道大学病院感染制御部
石黒 信久 部長
鏡 圭介 薬剤師
東京大学大学院工学系研究科附属水環境工学研究センター
北島 正章 特任教授
札幌市下水道河川局事業推進部
渡邊 浩基 処理担当部長
研究参画医療機関
北海道循環器病院
北海道大学病院
札幌北楡病院
札幌白石記念病院
北札幌病院
恵佑会札幌病院
恵佑会第2病院
札幌心臓血管クリニック
イムス札幌消化器中央総合病院
華岡青洲記念病院
愛全病院
札幌徳洲会病院
論文情報
雑誌名:Environment International
題 名:Association between confirmed COVID-19 cases at hospitals and SARS-CoV-2 levels in municipal wastewater during the pandemic and endemic phases
著者名:Keisuke Kagami#, Masaaki Kitajima#, Hiromoto Watanabe, Toshihiro Hamada, Yasunobu Kobayashi, Haruka Kubo, Seiko Oono, Hiromi Takai, Shuichi Ota, Tatsuya Nagakura, Toshiyuki Onda, Kanako Nagahori, Noriaki Sasaki, Ikuya Fujimoto, Akiko Sato, Sosuke Sumikawa, Daisuke Matsui, Yuka Ito, Megumi Baba, Tsuyoshi Takeuchi, Sumie Iwasaki, Toshinari Okubo, Satsuki Suzuki, Seiji Kataoka, Yoshiro Matsui, Yohei Inomata, Masaki Okada, Hisami Sanmi, Satoshi Fukuda, Naoki Wada, Kazufumi Okada, Yusuke Niinuma, Nobuhisa Ishiguro*
#equal contribution(共同筆頭著者)
*責任著者
DOI:10.1016/j.envint.2025.109342
URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412025000935
研究助成
本研究は、厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究事業)「旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究(課題番号:JPMH2024LA1006)」、JST未来社会創造事業「健全な社会と人を支える安全安心な水循環系の実現(課題番号:JPMJMI22D1)」、内閣官房 ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に係る事業企画「下水サーベイランスを活用した感染トレンド把握及び感染者数の推計に関する実証(課題番号:1001)」、札幌市 受託研究「下水サーベイランスを活用した感染トレンド把握等に関する検討」の支援により実施されました。
用語解説
(注1)下水疫学調査
「下水疫学」は下水中のウイルス等の測定に基づき集団レベルの疫学情報を分析する学問分野である「Wastewater-based epidemiology」の訳語であり、北島特任教授と山梨大学の原本教授が考案。現在では、当該分野を指す用語として広く普及している。「調査」を付けることで、調査する行為そのものを意味する。
(注2)流入下水
下水処理場で処理される前の下水のこと。
(注3)EPISENS-S法
北島特任教授(当時北海道大学)と塩野義製薬の共同研究グループが開発した下水中ウイルス高感度検出技術の一つである「Efficient and Practical virus Identification System with ENhanced Sensitivity for Solids」の略称。なお、「EPISENSTM(北海道大学の登録商標)」には「疫学(epidemiology)情報を高感度(sensitive)に検知(sensing)する手法」という意味が込められている(【関連情報:プレスリリース②】参照)。
(注4)下水サーベイランス
下水中の病原体等を検査・監視することであり、下水疫学調査と概ね同義であると考えて良い。札幌市は、市中の感染状況を把握し感染症対策への活用可能性について検討を行うことを目的として、2021年2月より下水サーベイランスを継続的に実施している。下記の札幌市ウェブサイトにて調査概要及び結果を確認可能。
(https://www.city.sapporo.jp/gesui/surveillance.html)
プレスリリース本文:PDFファイル
Environment International:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412025000935
おすすめ記事
本件に関連する記事はこちら

検査数の減少で見えなくなる感染拡大 ―下水サーベイランスが明らかにした“報告されない感染”の実態―
東京2020オリンピック・パラリンピック選手村でCOVID-19の下水疫学調査を実施 ~下水疫学調査の社会実装と大規模集合イベントにおける感染対策の一環としての活用に期待~