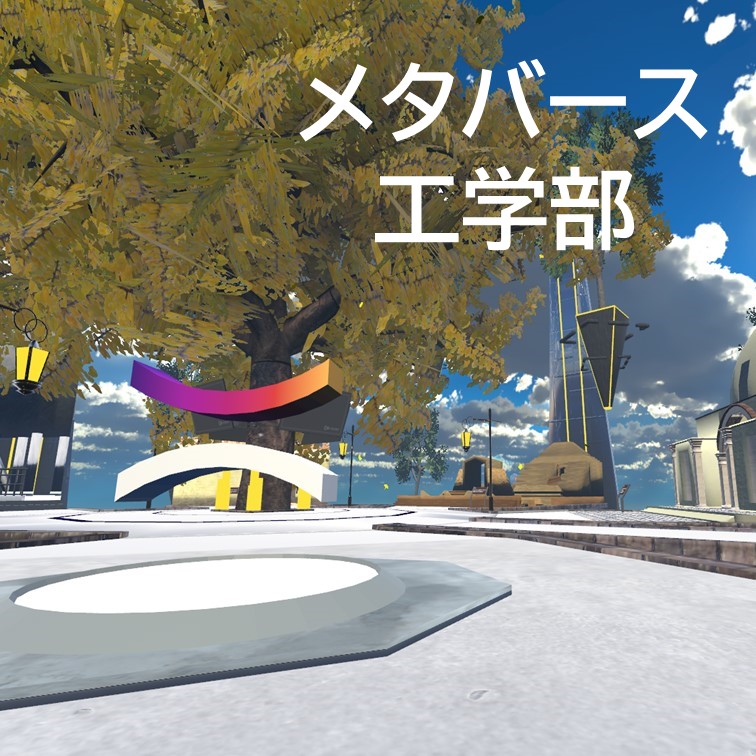東京大学工学部 進学選択ガイダンス - 概要 -
目次
工学では社会の中での科学技術を重視している。今日の社会は、科学技術の成果を利用せずには一日たりとも機能しないことは明らかである。また先端科学は工学技術に支えられている。
生活環境が整い医療が高度化することによる高齢化社会の到来、大量消費による資源の枯渇や環境の汚染など、私たちが立ち向かわなければならない問題が沢山ある。工学の教育・研究に携わる私たちは、科学技術が社会の中で活きてこそ意味があるという工学の原点から、様々な取り組みを行っている。その守備範囲と手法は限りなく広範である。原子レベルでの物質の理解から、それらを組み立て構造化する技術まで、情報の意味を考えることからは情報の効果的な伝達・処理技術まで、さらにこれら全ての技術が及ぼす社会的影響の評価に至るまで。私たちはそれぞれの取り組み方で創意工夫し、工学の一翼を担っている。
大学院工学系研究科・工学部の概要
| 設立 | 明治19年(1886)帝国大学工科大学として7学科を設置 |
|---|---|
| 組織 | 部局としての大学院と併設された工学部よりなる |
| 学生数(2024.5.1) | 学部 2,171 名 大学院 修士 2,302 名 大学院 博士 1,451 名 |
| 教職員数(2024.5.1) | 教授・准教授・講師・助教・助手 594名 事務部等 222名 |
| 予算額 | 約333億円(2023年度) |
| 大学院専攻 | 18専攻および客員講座、寄付講座 |
| 学科 | 16学科 |
| 附属施設 | 総合試験所(昭和14年10月開設)→ 総合研究機構に改組(平成14年1月) |
工学を学ぶ意義
工学の意義
工学は自然、人間、社会の諸法則に関する真理探究に止まらず、その結果を総合的に組みあげて、人間の生産的実践に役立てようとする。このためには素材としての材料、それを動かすエネルギー、そして、これらを有効に組み合せる理論としてのシステムの研究があり、これらを総合したところに工学の独自の理論がある。人間は生産的実践諸分野のいろいろな段階で判断を迫られる。設計はその一例であってその過程は判断の連続であるといってよい。
工学は、判断を下すために客観的資料を揃え、決定をする総合性をもつ科学技術である。分析よりも総合の学としての工学は、基礎から応用まで学問の広い領域、方法を含み、また対象を拡げていく可能性をもっている。このために近年、工業以外の場にも工学的手法が浸透しつつある。人間工学、教育工学、社会工学、医工学、経営工学などの諸分野が例としてあげられる。高度成長社会で公害をまき散らしたり、欠陥製品を出したり、交通問題など社会問題を発生させ、激化させたのは、特にわが国の現代文明の中で工業、工学などが異常に発展したせいであるとする議論がある。この点については、工学として総合的視野に立った予測、判断に甘さや弱さがあったこと、人文、社会諸科学との学際協力に立って工業化社会の展開について最適解を求め政策、世論に提案をしなかったこと、などに高度産業化社会の困難の一因があったと考えられる。
このような経験を通じて、工学は社会における工業のあり方、工学の意義、役割を改めて問い直し、一層、総合的な視野、判断をもつ科学として脱皮しつづけている。 工学は、人間が道具をつくり始めた技術の起源と共に長い歴史をもち、同時に絶えず脱皮、発展をつづける若い体質をもっていると言えよう。
人間実践に合理的基礎を与えるものが工学であり、この上に工業が成立する。この意味では、医療、農業などを始めとする広い分野がさらに工業化されていく。人間社会の多くの分野で、どのようにして良い方向に社会を発展させていくかという問題に対しての責任を工学は担っている。
工学には未開拓分野も多く、工学、工業に関して固定観にとらわれることなく学問的関心を寄せていただきたい。
工業界の現状と将来
わが国は、19世紀半ばから100余年の間に、一小農業国から世界最大の工業国の一つへと成長した。この間における工業化の規模と質の変化の度合、速度は世界史に例を見ないものであった。多くの発展途上国が、わが国の近代化に深い関心をもっている主たる理由はここにある。とりわけ60年代から70年代前半における高度成長期は驚くべき時代であった。その結果、国内に豊かさと、その裏に様々な社会問題を歪としてもたらし、対外的には途上国のみならず先進諸国との間にも摩擦を生じたのである。
しかし、狭い国土に多数の人口を擁する超高密度社会で、資源、エネルギー、食糧が絶対的に不足しているわが国で、今後とも国民の生活を支えていく上での工業の存在は欠かせない。そればかりでなく、世界的な規模で人間の生活を寄り豊かにするためには、高度な産業の発展が欠かせないことはいうまでもない。
その産業のあり方が、19世紀以来の高度成長がもたらした結果によって国内的にも、国際的にも問われているのが現状である。今後のわが国工業のあり方をもっとも深刻に考えているのは工業自身であり、もっとも展望をもって工業のあり方を予測しようと努力しているのも工業自身である。資本、資源、労働力の量よりも人間の知恵により大きく依存、立脚する工業のあり方を見出そうとしている。この課題は、工学に従事する者にとって困難ではあるが、学問的に極めて興味があり、かつ生きがいのある仕事である。
技術者の使命と地位
工学部の卒業生は、社会に出ると徹底した専門的職業教育と訓練を実践の場でうける。新しい知識・技術を習得するのもこの時期である。年齢的には、20代の終りから30代、40代においては、錬磨した技術者として最先端の研究、技術開発、製品開発、あるいは新型プラントや機械の設計、建設整備に活躍する。当初は中堅の技術者として、何年かたつとチームのリーダーとして働く。しかも、この間は自分の職場においてだけでなく、学会、業界、政府等の委員会及び国際的な活動の場においても活躍して社会に大きな貢献をする。50代以後の技術者は、どの分野にあっても国際的視野にたっての研究、技術、製品等の新開発の目標、方向を決定し、それに向って組織を指導管理する。
以上が工学部の出身学科、就職分野を問わず共通して見られる技術者のキャリア形成である。このキャリア形成を通じて技術者の発言力がしばしば問題になる。正しい主張、提案、警告も、説得力と発言力を伴っていないと有効に作用しない。どの職域においても、技術者の生涯は自らの主張に発言力を持たせ、仕事のために適切な条件を獲得する闘いの連続である。「工学の意義」でのべた総合的な判断「力」によって、永年にわたって自ら訓練した優れた技術者が大きな組織の最高指導者となっている例は多い。
人間活動のあらゆる分野に工学的思考が滲透しつつある状況において、将来は、社会のより多くの分野で、より重要な役割を果たす技術者が多数育っていくことを社会は期待している。
工学部への進学
一般的注意
進学関係の詳細な情報は、入学時に配布される「履修の手引き」に記載されているので、これを参照してほしい。
また、2年生の夏学期中に駒場で開かれる学部ガイダンス(工学部の各学科の紹介)、及び進学ガイダンス(進学手続きの説明)に参加すれば、諸君の進学に当たっての方針決定に非常に参考になるであろう。
さらに、諸君に工学部各学科について十分な知識を与え、かつ進学の相談相手となるために、工学部各学科では進学指導教員をおいて進学問題について個人的な指導・相談に当たっている。進学指導教員に面接したい場合には、担当教員名簿(教養学部報に発表される。駒場キャンパスの進学相談室でも分かるし、工学部各学科の事務室に問い合わせても分かる。)および連絡方法が示されているので、それを活用してほしい。
進学選択部門と学科・コースとの対応関係
進学選択部門と学科・コースとの対応については、下の表を参照されたい。選択部門とは、2年生の選択時に進学定員を決める専門別の枠をいい、学科とは、工学部運営上の区分で、学生の所属の単位となり、その中に学生の修学上の区分けであるコースがある。これらの三者の関係は各学科によって異なることがあるので、詳しくは各学科の紹介記事を参照してほしい。
進学選択部門と対応学科との関係
学 部 | 学 科 | 部 門 | 定 数 |
工学部 984名
| 社会基盤学科 | 社会基盤学科A (設計・技術戦略) | 51 |
| 社会基盤学科B (政策・計画) | |||
| 社会基盤学科C (国際プロジェクト) | |||
建築学科 | 建築学 | 57 | |
| 都市工学科 | 都市環境工学 (環境共生・国際公共衛生・水・環境バイオ) | 53 | |
| 都市計画 (都市と地域の分析・計画・デザイン) | |||
機械工学科 機械情報工学科 | 機械工学A (デザイン・エネルギー・ダイナミクス) | 92 | |
| 機械工学B (ロボティクス・知能・ヒューマンインターフェイス) | 41 | ||
航空宇宙工学科 | 航空宇宙学 | 55 | |
| 精密工学科 | 精密工学 (知的機械・バイオメディカル・生産科学) | 45 | |
電子情報工学科 | 電子情報工学 (計算知能・コミュニケーション・メディアデザイン) | 61 | |
電気電子工学科 | 電気電子工学 (エネルギー&環境・ナノ物理・電子&光システム) | 62 | |
物理工学科 | 応用物理・物理工学 (物性物理・量子情報) | 52 | |
計数工学科 | 計数工学・数理/システム情報 (数理工学・物理情報学・認識行動学) | 60 | |
| マテリアル工学科 | マテリアル工学A (バイオマテリアル) | 78 | |
| マテリアル工学B (環境・基盤マテリアル) | |||
| マテリアル工学C (ナノ・機能マテリアル) | |||
| 応用化学科 | 応用化学 | 53 | |
| 化学システム工学科 | 化学システム工学 (環境・エネルギー・医療) | 46 | |
化学生命工学科 | 化学生命工学 | 49 | |
| システム創成学科 | システム創成A (環境・エネルギーシステム) | 129 | |
| システム創成B (システムデザイン・マネジメント) | |||
| システム創成C (知能社会システム) |