トピックス
- スポットライト
- 研究
- 2022
【第14回 インタビュー】 原子力国際専攻 佐藤健先生
100京分の1秒「アト秒科学」で解き明かす電子の運動
―紙と鉛筆だけで世界を驚かせる新理論を創り出す―
化学反応、物質の根本的な働きという部分で物理学の世界とつながっています。電子という量子のふるまいを計算で解明すれば、生物への放射線の影響を解明することもできるといいます。染谷隆夫工学系研究科長が研究の成果と未来、発展のために必要なことについて語り合う対談の第14回では、大学院工学系研究科原子力国際専攻の佐藤健准教授に、電子の世界のタイムスケールと物質科学について語っていただきました。
染谷:佐藤先生は、量子コンピュータと、アト秒科学という、人間の認識を超えた工学の最先端を取り扱う研究を2つもされています。まずは、発展中の量子コンピュータによってどのような研究が可能になるのか、ぜひその現場について聞かせてください。
佐藤:現在私は、2021年7月に川崎市で稼働開始し、IBMと東京大学のパートナーシップで利用できる「IBM Quantum System One」という量子コンピュータ(研究チームでは愛着を込めて「Kawasaki」と呼んでいます)を使って、化学反応の基礎である電子の運動を解きあかす量子力学シミュレーションを始めています。電子は物質を形作る原子を構成するもので、たとえば物質に光が当たったときに光のエネルギーを最初に吸収するのは電子ですね。この電子がアト秒―あとでこの時間単位について詳しく説明します―の単位で動き回ると、原子核に電子の運動エネルギーが移行して、化学反応がおきたり、分子が壊れたりします。物質の性質を決めているのは電子なのです。
電子は量子のひとつですが、「古典コンピュータ」といわれる従来の計算機でこうした電子のふるまいをシミュレーションしようとすると、計算量が指数関数的に増えて計算コストが膨大になってしまいます。量子コンピュータは量子の性質そのものを使って計算するため、こうした計算コストの増加がありません。現状はまだ量子コンピュータの機能に制約がありますが、うまく使うことができれば、本当に大きな分子を扱うなど、10年、20年後に世界が変わるシミュレーションができる可能性があります。
染谷:従来の、古典コンピュータでは計算量が膨大になってできない計算が量子コンピュータならば可能になるわけですね。電子という量子のふるまいを量子のまま計算するというのは、どのように計算するのでしょうか?
佐藤:まず、量子コンピュータには「量子ビット(qubit)」という基本単位があります。古典コンピュータの単位、「ビット」は0か1か、という2つの状態を表しますが、量子ビットは0と1の「重ね合わせ状態」を表現できます。電子の運動を計算する場合、電子の軌道ひとつひとつを古典ビットで計算する場合、「ない(0)/ある(1)」にそれぞれビットを当てるので2のn乗の計算になりますが、量子ビットならば2のn乗ではなくn個、つまり量子ビットの数で表現できます。
「Kawasaki」などの量子コンピュータが内部で実際に何をやっているかというと、まず量子ビットをたくさん並べた多量子ビットの初期状態を作ります。次にこの多量子ビット状態を、ユーザーが書いた量子回路図に従って時間発展(時間の経過による変化)させます。(量子回路については後で説明します。)そして最後に時間発展の後の量子状態を「観測」します。量子コンピュータで量子ビットの状態が変化するのと、実際の電子のような量子系が初期状態から時間とともにどのように発展していくか、ということには深いアナロジーがあって、量子コンピュータと量子系のシミュレーションはとても相性が良いのです。そのものといっても良いくらいです。
染谷:量子コンピュータを使うと、まるで量子を扱う実験をしているかのように答が得られるように思えてきました。ただ、量子コンピュータで計算する場合はどのように操作するのでしょうか? 「Kawasaki」はヘリウムで物質を極低温まで冷やして超電導状態を作り出す方式ですが、佐藤先生はヘリウムを扱っているわけではないですよね。プログラムを書いて、量子コンピュータへ送るのですか?
佐藤:そうですね。「Kawasaki」は東大を中心としたコンソーシアムから利用しますが、それだけでなく世界中にフリーでアクセスできるIBMの量子コンピュータがたくさんあります。そうした量子コンピュータを、いわばクラウドコンピュータを利用するようなかたちでプログラムを書いて送るわけです。プログラムは、「量子回路」という設計図のようなもので、これが実行されるとたくさんの「観測結果」をカウントした、ヒストグラムのような形で返ってきます。
染谷:回路図というのは、プログラム言語を図で描いたようなものですか? 私の専門は電子工学なので回路図を描いて、「NOT」や「AND」を組み合わせながらロジックゲートを組み上げていたわけですが、量子コンピュータもそのあたりは似ていますね。
佐藤:量子コンピュータも基本的なNOT、AND、OR のような少数の演算素子ですべての量子ゲートを実現できるので、古典コンピュータとその点は同じですね。IBMなど量子コンピュータの運用元が提供してくれたソフトウェアを使って回路図を描いた後、「トランスパイル」という操作を行なって「Kawasaki」などで実行可能なゲート操作に書き直します。コンパイルと似たような作業です。これでようやく、量子コンピュータの実機で回路を実行することができるわけです。
2つの量子ビットで計算する場合を考えてみましょう。量子ビットに対して、古典コンピュータでいうところの0を1に反転させる「NOTゲート」や、「コントロールNOTゲート」といった何か目的を果たすための操作を置くことができます。そして、最終的にどういう状態が得られたのか、「答」を読み出してください、という流れでひとつの回路図を完結させます。最後の読み出しが「観測」です。最初が00で、量子ビットが2つの場合は00、01、10、11のどれかになります。「ショット」といって、回路を1000回というように何度も実行していって、最終的にどのパターンが得られたのか、ということをカウントしていくわけです。
染谷:答がヒストグラムで返ってくるというのはなぜでしょうか?
佐藤:量子力学の教科書にある通り、1回観測するとこの状態が得られる、もう1回観測するとこの状態が得られる、というように観測によってバラバラの値が得られるのです。(教科書に書いてある通りでちょっと感動的です。)こうして得た答のカウントを自分の古典プログラムで解析して、ようやく必要な情報が取り出せるのです。途中の操作を変えると、最後の状態を望みの状態に変えることができたり、どれか1つの状態のカウントを非常に大きくすることで、組み合わせ最適化の問題を解いたりすることができます。こうした手法が「量子アルゴリズム」といわれるものです。
染谷:量子コンピュータの使い方がだんだんイメージできるようになってきました。量子コンピュータは、佐藤先生のような電子の時間発展の計算や、先程挙げられた組み合わせ最適化問題を解く場合に相性が良いということもわかってきました。量子コンピュータで、すでにさまざまなことができるようになっていて、もう古典コンピュータを超えている部分があるように思います。ただ、何もかも量子コンピュータで解決するには、まだハードルが存在するわけですよね。
佐藤:はい。完璧な量子コンピュータというものが完成すれば、すべて解決されるのかもしれませんが、それはかなり遠い未来で、現状では量子回路の操作に0.1%くらいのエラーがあります。古典計算でもエラーは起きますが、エラー訂正は決定論的なので比較的楽にできます。一方で量子力学に基づく操作のエラーというのはそれ自体がランダムなので、量子エラー訂正というのはものすごく難しくてまだ確立していないのです。これを実現するには、何百万という量子ビットが必要だとされていますが、「Kawasaki」ではまだ20数量子ビットです。現状では、エラーが大きすぎて非常に工夫しないとシミュレーションもできません。ハードウェアの発展と歩調を合わせないと、まだ量子コンピュータは勝負にならないのですね。
染谷:そうした量子コンピュータの発展は、20年も30年も先だと思われていました。最近では急に加速して注目されているように思えますが、これはなぜでしょうか?
佐藤:一つには、量子エラー訂正に対する考え方が変わってきたという事情があります。以前は、量子エラー訂正ができないと万能量子計算はできないので、それまで待たなくてはならないと考えられていました。それが2010年代ごろに流れが変わって、完璧な量子コンピュータが作られるまで待つよりも、NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)デバイスといって、今ある量子コンピュータでも可能なアプリケーションを探していこう、という考え方になったのです。ノイジーというのはエラーがあるということで、また何百万量子ビットではなく、数十量子ビットと小さくてもいい。そこでIBMが世界中に無償で利用できる量子コンピュータをクラウド提供してくれるようになった。途中でエラーがあったとしても、短い、古典コンピュータではできないことをやってみようという理論研究、実証研究が爆発的に増えてきています。おかげで一気に盛り上がって、現実的になったという印象なのだと思います。
染谷:真理を追求すると完璧なものができるまでは利用が始まらない、というメンタリティになりますが、工学は実学的ですから、走りながら良くしていこうと考えて発展が加速したわけですね。何かうまくいった成功事例というものはありますか?
佐藤:古典コンピュータで解けるけれども、それほど自明でない問題を量子コンピュータで解いてみましたという例が増えてきました。特に、時間に依存しないほうのシュレーディンガー方程式は、量子化学としてNISQの筆頭アプリケーションということになっています。
染谷:量子コンピュータは量子の性質と相性が良いので、物性の素過程を解いて物質の変化を予測したり制御したり、といったことが可能になるわけですね。この物質の性質を解明する研究では、佐藤先生は「アト秒科学」というレーザーの超短パルスを使ってさまざまなものの性質を調べる最先端の研究も取り組まれていますね。ここからはその研究についてうかがいたいと思います。
「電子の時間スケール」で物質を理解する
染谷:アト秒というと、ピコ秒、フェムト秒という非常に小さな時間の単位よりもさらに小さく、10のマイナス18乗(100京分の1秒)という単位です。光でさえ、1アト秒に45ナノメートルしか進むことができないわけですね。そうしたレーザーの科学の最先端では、どんな世界が切り開かれているのでしょうか?
佐藤:アト秒の10のマイナス18乗という時間は、人間にとっては認知することも難しい時間ですが、分子や固体の中の電子の動きにとって自然な時間スケールです。たとえば、「ボーア半径」という、水素原子の周りを電子が一周する時間が152アト秒です。
ですから、アト秒パルス幅のパルスレーザーは、アト秒でコマを切れる非常に速いシャッターを持つカメラだと考えることができます。物質の中の電子がどう動いているかを直接見ることができるようになった。それがアト秒科学の醍醐味です。
先ほど、「物質の性質を決めているのは電子」といいました。最初にアト秒スケールの電子の運動があり、それが分子の運動につながります。ですから、最初のアト秒の電子の運動のところをコントロールできれば、その先でどのような化学反応が起きるのか、分子1個単位で究極的なコントロールが可能になると期待されているのです。まだ夢の世界ですが、世界中の物理、化学、生物学の人たちが参加してきています。
染谷:すると、化学反応の素過程が解明できるようになり、電子運動のレベルで観測、制御ができるという研究のターゲットが見えてきたわけですか?
佐藤:物質に強いパルスを当てると、電子がイオン化して飛び出してきます。ただ、強いパルスは振動電場なので、飛び出していった電子は空間中で大きく揺さぶられて、あるものはもとの分子のところに戻ってきて、再結合します。このとき、電子はレーザーから獲得した余剰エネルギーを光として放出します。これを「高次高調波発生」といい、この高次高調波はアト秒パルス発生源の一つです。
私はこの10年ほど、アト秒パルスや超高速電子運動を、理論的に、またはシミュレーションで理解し、こうした問題を解くための新しい理論や計算方法の開発に注力しています。
染谷:アト秒で光と物質の相互作用の電子運動を見る場合、新しい計算方法はどの部分に関わってくるのでしょうか?
佐藤:「新しさ」にかかわる部分は大きく分けて2つあります。まず、時間依存の量子力学の問題を解くということそのものが非常にチャレンジングで、そのための計算方法の開発というのはとても重要です。
染谷:どの点がもっとも難しいのでしょうか? 計算式ができれば、計算機の進歩で解けるというものではないわけですね。
佐藤:物質の中には電子がたくさんありますので、この多粒子系というところが大きな問題です。水素原子の場合は、現在のノートパソコンでも正確に解くことができます。ですが、量子力学の計算コスト、量子次元の数というのは電子の数が増えると指数関数的に複雑さを増し、解くのが難しくなります。先程の量子コンピュータを利用するようになった理由もここにあります。
染谷:たくさんの電子が相互作用している状況を計算しようとすると、天文学的に難しくなってしまうわけですね。ただ、平均的な場があって、水素原子のように電子の数が少なくて、1個や2個の電子ならば解けるわけです。1つ2つと、解けなくなるほどたくさんの電子、難しさにグラデーションがあるならば、量子コンピュータでなければ解けない部分ばかりではないのではありませんか?
佐藤:たしかに、すべての電子を正確に取り扱う必要はなくて、平均場的に扱うというのはとても良いアイディアです。外から光が入ってくると、全ての電子ではなくエネルギーの小さな電子だけがアクティブに応答するのですね。そこで、エネルギーの小さい電子だけはしっかり量子相関を取り入れて解く、そしてそれ以外の電子は平均場として捉えるという方法はあります。クリプトンという原子の場合、赤外レーザーを当てたときに36個中の8個の電子しか扱わなくても精度のよい計算ができる、ということがわかっています。
染谷:物性や化学反応を調べる場合、主として寄与するエネルギーレベルにある電子だけを選択的に取り出すことで、計算量を抑えて有限の計算時間で解けるようにすることができるわけですね。すると、新しい計算の方法を新しく開発する腕の見せどころというのはその選択にかかわる部分でしょうか?
佐藤:まずは、柔軟に選択できるような理論的枠組みを作る必要があります。電子というのは量子力学的な性質を持ち、原理的に区別できないですから、電子を選択するというのは実は難しいのです。そこで、区別が難しい多体粒子系の中の一つの部分を区別して計算できるような理論を構築する必要があります。理論ができたら、実験を行う人たちとコラボレーションして、実際にその計算を利用してみます。たとえば最外殻の電子だけ扱う、電子の数をもう少し増やしてみる、などですね。すると計算結果が変化することから、だんだんとどの電子が大事だったのか、という物理的な内容に洞察を与えることができます。
染谷:たしかに、実験では任意の電子だけ勝手に抜いたり足したりはできないですね。シミュレーションを使って、実験を行う分野にサジェストを与えられるというのは大事なことです。これが先生の最初の腕の見せどころ。では2番目は?
佐藤:2番目に、アト秒という非常に短い時間スケールの科学を、社会に役立つものにしていくということです。役立つという視点では、アト秒の電子の動きがフェムト秒やピコ秒スケールの分子全体の運動にどう伝わるかまでシミュレーションする必要があります。そこで、電子と分子中の原子核すべてを量子力学的にシミュレーションする方法の開発を続けています。
ここでもポイントは柔軟な方法論を開発するということです。分子を量子力学的に扱うといっても、大きなタンパク質分子の中のすべての原子核を量子力学的に扱うのは、おそらく永遠に不可能だと思います。分子中の重い原子は古典力学的に扱い、プロトンのように必要な部分だけを量子力学的に扱う。同じ分子であっても、量子と古典の切り分けをコントロールできるような理論を作っています。すると、計算コストが実現可能なものになります。また、プロトンを量子力学的に扱う場合と古典力学的に扱う場合を比較してみると、DNA分子の中の水素移動に量子性がどのように効いてくるのか、といったことが理論で扱えるようになります。
染谷:アト秒の科学によって、生体の中で起きている化学反応を解明できるようになるわけですね。ただ、社会に役立つ分野には、多くの科学者が参入して競争が激しくなると思います。その中で、佐藤先生オリジナルの、強みのある部分はどこでしょうか?
佐藤:私の最大の功績は、「時間依存多配置理論」といって、たくさんの電子がたくさんの軌道にいろいろな詰まり方をする、その「配置」の重ね合わせでレーザー中の電子の運動をシミュレーションできるようにしたことです。最初はほとんど基底状態ですが、外からレーザーパルスが当たると励起する電子が現れて、配置の重みが変化していきます。さらに、配置の重みだけではなくて、電子ひとつひとつが占有する軌道そのものも時間発展させるような方法も開発することができました。すると、イオン化して電子が飛んでいってしまうようなシミュレーションもできるようになった。これがブレイクスルーであり、私のオリジナリティです。
染谷:強い、単パルスをあててイオン化した分子をシミュレーションする場合に、その過程を理論的に見せられるようになったわけですね。
佐藤:そのとおりです。10年前に、石川顕一先生と共同の研究室を始めたときは、電子2個のヘリウム原子が限界でした。それでも電子1個の水素原子よりとても難しかったのですが、現在は電子が数十個あってもイオン化を伴うようなシミュレーションができるようになりました。
染谷:アト秒科学の本質に迫るシミュレーションを成し遂げられたわけですね。世界の人たちが競争している中で、それほどすごいことが可能になった決め手は何でしょうか。
佐藤:この分野はもともと、世界の原子物理学の研究者が扱っていたもので、2電子、3電子を正確に解く、という少数多体系の考え方で取り組んでいました。一方で私は応用化学の出身で、理論化学の平尾公彦先生の元で、たくさんの電子に対して時間に依存しないシュレーディンガー方程式を解く技術を学んでいて、それを時間依存する問題に拡張するという方針がうまくいったのです。異分野の考え方を先陣を切って持ち込むことができたのが強みになったのだと思います。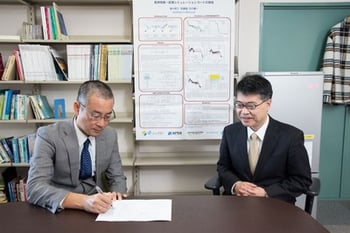
染谷:物理と化学の境界領域である分野に、化学の新しい手法を持ち込んだことで時間変化が見えるようになったわけですね。そのように、分野をつなぐ発想を持って研究者の道に進まれたのはどのようなきっかけからでしょうか。
佐藤:私は長野県の諏訪湖の近くの水のきれいな茅野市で育って、生き物と理科が大好きでした。東京大学に入学したときから、細胞生物学などの分野の研究者になろうと思っていたのです。ただ、大学生だった1990年代後半はPCの普及期で、デスクトップPCを手に入れて、生物も楽しいけれどもロジカルなサイエンスの物質科学は面白いと思うようになりました。そこで応用化学に進み、平尾先生の「化学は計算できる」という講義に感銘を受けたのです。物質科学の理論とシミュレーション研究を目指すようになって、博士号を取得した後は理論化学の研究室でポスドクしていたのです。ただ、化学は非常に正確に、kcal/molといった単位で精密にものごとを解く必要があります。それよりもっととんでもないこと、激しいことをやりたいと感じるようになってきて、東大で高強度レーザーや超短パルスという分野で募集がありましたので、時間に依存する現象のダイナミクスの世界に魅力を感じて、挑戦してみようと思いました。
染谷:計算で化学反応を知るという研究に魅力を感じられたけれども、精度を追求するよりも異なる展開に関心を持たれたわけですね。その「とんでもないこと」の方向として、アト秒パルスや時間依存の方向性を追求されたわけですが、平尾先生の基本はあるにしても、未知の分野に飛び込んでチャレンジしようと思ったのは何が背景でしょうか?
佐藤:化学の分野でも、電子は時間に依存しないけれども、分子のレベルでは時間に依存する「第一原理ダイナミクス」という方法があります。ただ、電子は、時間に依存しないシュレーディンガー方程式を解くけれども、分子の運動は時間に依存する、という研究をやってみると、なんだか始まり方が不自然に思えたのです。分子中の原子を少しだけ動かすというシミュレーションにしても、最初は手でぽんと叩くように、人工的に何かを始めないといけない。それは変なので、そもそもの始まりからシミュレーションしたい。すると、その始まりというのはやはり電子なのです。そこで、電子についても時間依存の問題にチャレンジしたいと思って、その視点で課題を探したのがきっかけですね。
染谷:それはとてもわかりやすいですね。電子は時間に依存しない、けれども分子のシミュレーションをしてみると、キックオフの電子が動くところも時間に依存しないと違和感がある。科学者としての素朴な感覚がきっかけになったのはとても良い話です。
佐藤:当時は、できるという確証があったわけではなかったのです。化学の分野には大きな市場があって、計算が役に立つ先が確立されていますが、このシミュレーションというのは役に立つかどうかわからない。アト秒で電子をコントロールしたいといってもまだ実現していないわけですし、その不確実なところに突っ込むのは、「よく考えたほうがいい」と平尾先生からは忠告されましたね(笑)。向こう見ずで、楽観的なところがあったかもしれませんが、それでもやってみようと思いました。
染谷:専門家が難しいと意見されたことではありますが、かといってそこでやめてしまったら新しい世界は切り開かれないわけですね。意見には耳は傾けるけれども、向こう見ずなチャレンジをしてみるところがないと新しい分野は開かれないのだと思います。もしかすると、平尾先生に今うかがってみれば「奮い立たせるために引いた視線で意見したんだよ」とおっしゃるかもしれませんね。
さて、佐藤先生は最先端の技術を駆使しつつ、物質の素過程を解明する研究に取り組まれて成果を上げておられるわけです。これから、解き明かした量子の世界の科学は、どのような方向に活用されていくのでしょうか?
佐藤:私は工学部にいながらもピュアサイエンスに近いことをやっていますが、その先には所属する原子力国際専攻が推し進める原子力工学という分野があります。レーザーも含めて、光というのは電磁波の一種ですが、原子力工学がターゲットとする放射線のうちたとえばガンマ線も電磁波の一種です。かたや、電子というのはフェルミ粒子という量子力学的粒子の一種ですが、原子核中の陽子や中性子も量子力学的粒子の一種です。レーザーと電子がターゲットだったこれまでの研究を大きく拡張して、いろんな電磁波やいろんな量子力学的粒子が交錯する問題に挑んでいます。専攻内や学内・学外の先生方や仲間と協力して、放射線の医療応用や生物影響といった、応用工学的な研究にも取り組んでいます。
染谷:物性の素過程から物質の状態の予測を理解し制御するために、量子コンピュータが進歩していくのは自明のことと思われます。そして佐藤先生は、ご自身の根源的な関心である生物の世界にその研究成果を応用しようと考えられているわけですね。量子コンピュータとアト秒科学という最先端の分野を使いこなし、工学的課題にも取り組まれている先生のご研究は、研究科としてとても誇らしいですね。
東京学芸大学 附属竹早中学校(東京都)出身、東京学芸大学附属高等学校(東京都)出身

