トピックス
- スポットライト
- 研究
- 2021
【第8回 インタビュー】総合研究機構/バイオエンジニアリング専攻/化学システム工学専攻 太田誠一先生
「機能性ナノ粒子」の力を医療分野で引き出す技術
―化学工学の知見で実現する、がん治療から早期診断まで―
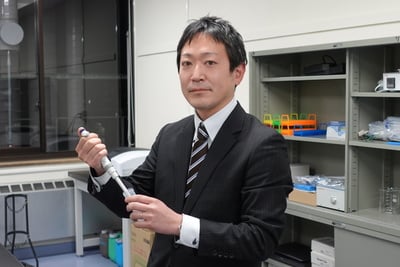
ヒトの体は化学プラントだった。100万分の1ミリの粒子を駆使して、がんを治療し疾病の早期診断を可能にする技術の実現には、工学の考え方で生体を捉え直す発想がありました。 染谷隆夫工学系研究科長が研究の成果と未来、発展のために必要なことについて語り合う対談の第8回では、バイオエンジニアリング専攻の太田誠一准教授に登場していただきました。
ナノ粒子とDNAを組み合わせる技術
染谷:太田先生は、「体の中でナノ粒子を機能させ、病気を診断・治療する」という技術をお持ちだそうですね。そうしたことがなぜ可能なのか、またそれは薬による病気の治療とはどう違うのでしょうか?
太田:私は主に、光機能性の医療用ナノ粒子というものを開発しています。有機ELのポリマーをナノ粒子化して、光で癌を治療するといったことや、金のナノ粒子で、アルツハイマー病の原因物質のアミロイドβを選択的に標識・除去したりすることができます。さらに、これらの粒子を集積化して並べるという技術を得意としており、さまざまな粒子を組み合わせて集積化することで、機能制御の幅を大きく変えることができます。
薬で病気を治療する薬学と近い部分もあるのですが、固体の材料を目的に応じて化学的・工学的に設計できるという点が異なります。粒子の表面やサイズを精密に操作するのは工学ならではですね。
染谷:先生の精密なナノ粒子操作に関する論文が科学誌『Science』に掲載されましたね。世界でもトップレベルの科学誌に評価された、先生ならではのオリジナルの技術はどのようなものでしょか?
太田:金のナノ粒子の表面にDNAを修飾して、これと相補的な配列を持つDNAを混ぜてやると、任意の形に粒子を配列することができます。これをうまく使うと、ある疾患に関連するDNAがあったときだけ、粒子の配列、つまり“形”を組体操のように動的に組み替えることができるのですね。形が変わることによって粒子間の距離が変わり、光特性をシフトさせたり、がん細胞に取り込まれるようにさせたり、といった操作ができます。
金ナノ粒子の表面にDNAを精密に修飾させるには、数や位置をコントロールしなくてはなりません。このとき、DNA同士の強い静電反発が障害となります。私はもともとコロイド化学が得意だったので、溶媒のpHや塩強度などを調整することでDNAの静電反発を抑えつつ粒子が凝集してしまわないように制御を行い、高密度かつ精密に、粒子表面のDNA数をコントロールできるようになりました。修飾が精密だからこそ、サイズの異なる粒子をある比率、例えば6:1といった感じで混ぜると、配列される粒子の数を狙ったところに制御することもできるのです。
染谷:ナノ粒子というものは、ピンセットでつまんで操作するということはできないわけですが、それを精密にコントロールできるとはすごい。その精密さがあるからこそ、疾病から人を助ける技術を発揮できるようになるわけですね。どのような治療に応用できますか?
太田:任意のタイミングで粒子の形を変えて光機能を発現させることで、さまざまな治療や診断が可能になると期待されます。例えば、光でがんを治療する光線力学療法というものがあります。病巣部分に光増感剤を集積させ、そこに光を照射することで活性酸素(ラジカル)を発生させてがんを死滅させる治療法です。光増感剤を体に入れて必要なところにだけレーザーを当てるのですが、どうしても正常組織にもある程度は増感剤が分布してしまうので、日常光にあたっただけでラジカルがでてしまうといった副作用があるのですね。そこで、光増感剤が腫瘍に近づいたときだけ機能が発現するようにしてやれば、選択的にがんだけを叩くことができるようになります。具体的には、光増感剤の機能を持つナノ粒子を中心にして、周囲に衛星状に金ナノ粒子をつけると、腫瘍の周りにあるときだけ衛星が外れて、抑え込んでいた光機能が発現します。すると光をあてたときにラジカルを出して、がんを叩ける。また、疾患に関連した分子(バイオマーカー)があるときだけ蛍光が発現するような設計をすることで、超高感度な疾患の診断も可能になります。
体を駆け巡るナノ粒子の流れをモデル化する
染谷:ナノ粒子の機能は、条件が揃うと自動的に発動するようになっている。どのような発想で、そういった技術を可能にされたのでしょうか?
太田:私の研究の出発点は、化学工学といって、プラント中の化学物質の輸送を数理モデルで理解して最適化するというものです。体の中というのは工場(プラント)と同じで、いろいろな臓器がパイプで繋がっていると考えることができます。
そこで、粒子を投入すると、どの程度の効率でどのように粒子が運ばれるか、ということをモデルをうまく作って再現して、設計を最適化して効率的にできるようにする。生体にはさまざまなスケール、階層があります。体の中を巡回した粒子が血管の隙間をどの程度通り抜けるのか、尿からどれほど排泄されるか、そうした全体を大きなモデルにしていく。多くの粒子を作らなくても最適になるように粒子の大きさを推算することができます。このような設計ができるのは、私のもうひとつの武器ですね。
染谷:たしかに、究極の化学プラントですね。人の体をプラントに見立てて数理モデルで解析し、最適化して生物の現象に応用することは過去に行われていなかったのでしょうか? それともある程度は進んでいたのですか?
太田:肝臓を”反応器”と見立てて代謝反応をモデル化する、といった試みは古くから行われており、低分子薬剤の体の中での振る舞いのモデル化も、薬学の中の「薬物動態学」でかなり近い視点から研究されてきたのですが、ナノ材料の振る舞いのモデル化はまだまだこれからです。対象の大きさが変わると、かなり難しさが変わって、低分子の場合は無視できたことが無視できなくなってきたりします。
染谷:数理モデルを使って、どうやってナノ粒子の設計を最適化するのでしょうか? こういうナノ粒子を作りたい、と数理モデルで予想すると、その通りに作れるものなのですか?
太田:例えばこれまでの研究で、超音波で脳の血管に隙間をあけてやって、隙間から粒子を通すことで粒子を脳に到達しやすくする、という検討を行っていたのですが、どの程度の粒子のサイズならばあけた隙間を通れるか、ということは事前にはわかりませんでした。そこで、いくつか実験をしてみます。小さければ小さいほどよく通るのかと思いきや、意外に中程度の20ナノメートル程度が最も良いということがありました。もっと小さな10ナノメートル、3ナノメートルではあまり通らない。ここで、化学工学で用いられる数理モデルを応用して解析してみると、粒子があまりにも小さいと隙間はよく通り抜けるものの、腎臓のフィルターも通ってどんどん排泄されてしまうことが分かりました。脳の隙間は通り抜けられるけれど、腎臓では排泄されない程度という絶妙なサイズが必要になるわけです。こうして最適なサイズを事前に決めることが出来れば、そのサイズに合わせて粒子を作ることは、私達にとってはそれほど難しくないです。
染谷:従来の薬剤とはまた違う考え方を化学工学という経験、知識から導入して、実際の治療に使えるナノ粒子を実現されているわけですね。新しい発想を取り入れられる土台になった経験はありますか?
太田:総合研究機構に着任する前は、医学系研究科の疾患生命工学センターに所属し、自分の専門であるナノ粒子に加え、伊藤大知先生のご指導の下、ハイドロゲルやスポンジ、不織布といった様々な医療材料の開発に従事していました。臨床のお医者さんたちと連携する機会が多くあって、臨床のニーズや、お医者さんがどう考えるのか、ということを学んだことが大きな財産になり、そこからいかに自分が培ってきた技術を臨床に活用するか、ということを考えるようになりました。医師と連携してみて痛感したことですが、現在は治療技術の発展によりかなりの病気は治るようになってきた一方で、発症してからでは治しにくい病気は依然として存在し、これに対応していくために、早期発見ということがますます大事になってきています。そこで、これからは疾患の超早期診断にフォーカスし、新たな分野に挑戦しようと思っています。生体分子というのは、私たちの体のバランスを保つ根底を支えていて、タンパク質だけでも1万種類以上の生体分子があります。どの分子も常に同じ状態にあるわけではなく、さまざまな分子が相互作用しながら、時々刻々と変化して体の調和を保っている。つまり、非常に健康状態を反映したデータなのです。現在の健康診断では、肝臓のγGDPのように、1、2個の分子をバイオマーカーとして基準値を越えているかいないかで疾患を判断しています。実際には、もっと全体の総和として健康状態をみると、単独のバイオマーカーでは兆候が捉えられない段階でも、なにかちょっとしたバランスが崩れているかもしれません。これを捉えられれば、より早期に病気を判定できるのではないかと思うわけです。より簡便で、より高感度に、マルチな生体分子を検出できる手法の開発というのが必要になってくると思います。
染谷:ナノ粒子を使って、早期診断の技術を実現するわけですね。どのようなことが可能になりますか?
太田:現在取り組んでいるのは、光機能性ナノ粒子を使って生体分子のプロファイル情報を正確に、かつたくさんとってきて、これを数理モデルで解析していくことです。健康な人のプロファイルと病気を発症する直前のプロファイル、どちらに近いのかをパターン認識して、患者さんそれぞれの生体プロファイルに基づいて疾患を判断できます。これまで培ってきたナノ粒子の精密合成技術を利用して、多種のバイオマーカーを一括で検出する技術を構築しつつあります。また、miRNAという新しいバイオマーカーの発現パターンを用いて、疾患の有無や、薬剤の治療効果の有無を判定する機械学習モデルの開発も進めています。これらを両輪として相補的に開発を進めていくことで、独自の診断システムを開発していきたいと思っています。
さらに、ただ混ぜるだけでこれらの生体分子プロファイルが検出できる技術が進めば、在宅迅速診断に近づいてきます。今、ニュースで聞かない日はない「PCR検査」ですが、これは酵素反応といって生体中での触媒反応に相当します。そこで、人工DNAを使って触媒反応を模擬してやると、酵素を使わない増幅反応系というものができます。金と蛍光ナノ分子が隣接していて光が出ない状態にしておいて、標的の核酸が1分子でもやってくれば触媒反応的に次々と金を引き剥がしていき、どんどん蛍光シグナルが上がって増幅される、といった技術を開発しています。まだ予備検討ですが、増幅反応の基盤は構築しつつあり、今後もっと先鋭化させて、ごく微量の疾患のマーカーでも光を増幅させて検出できる技術に発展できると期待しています。PCR検査は温度を上げたり下げたりする必要があるので、常温で混ぜるだけという検査のブレイクスルーになると思います。
もうひとつ、疾患に関連したタンパク質を標識した抗体の上で光機能性ナノ粒子の集積化を進めて、ナノ粒子をポリマー化させるという技術も開発しています。従来は抗体を蛍光色素で修飾することでラベル化・検出する手法が用いられてきたのですが、あまり多くの色素を修飾すると抗体の結合能が失われてしまうため、輝度に限界がありました。この方法ならば、抗体の結合能を損なうことなく非常に高輝度なラベル化ができて、高感度な抗原検査や画像診断などが実現します。粒子同士を精密にスペーシングできるので、蛍光分子が近接しすぎて消光してしまう、といったようなこともありません。
染谷:抗体の機能を阻害することなく、DNAをうまく使いながら粒子同士の近接を避けて長い鎖のようにつなげていく。これによって感度が上がると自宅でも簡便に検査ができ、自宅以外でも検査時間が短くなる。とても大事ですね。
染谷:ナノ粒子の働きが医療につながっていく先生の研究の根底に、数理モデルというものがありますね。その有用性というものを、どのように認識されてこの分野に入ってこられたのでしょうか? そして将来は何を成し遂げたいですか?
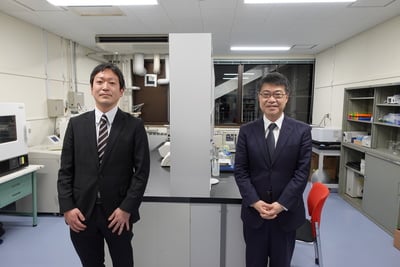
太田:私はもともと、卒論ではナノ粒子が流体の中でどう動くかというシミュレーションを研究していました。シミュレーションが描き出す世界、画像は美しいなと思って研究生活をスタートしたのですが、だんだんとそこから何に役立つかを考えるうち、医療はいいなと思ってきて、光るナノ粒子を合成するようになりました。
高校のときは、化学よりも物理や数式がすごく好きだったのですが、大学の講義を聞く中で数式というものは物理だけで使われているわけではない、さまざまなところで活用されていると思うようになりました。高校では物理の範疇だと思っていた数式はシュレディンガー方程式などの形で化学の基礎を成していて、これらをシミュレーションすることで目標とする出口に向かっていく。化学のそういうコンセプトがとても面白そうだなと。
最終的には、私が面白いと思っているナノ粒子が役に場面をもっと広げたいと思っています。面白さと役に立つこと、その両立をずっと大事にしていきたいですね。役に立つことの例として診断という仕組みがあり、これをしっかりと作っていきたいと今は強く思っています。
染谷:「面白い」と「役に立つ」は両方とも工学の重要な側面ですね。先生の目指すその方向を応援したいと思います。
Profile
太田誠一准教授
私立広島学院中学校(広島県)出身、私立広島学院高等学校(広島県)出身
聞き手:研究科長 染谷隆夫教授
東京学芸大学附属竹早中学校(東京都)出身、東京学芸大学附属高等学校(東京都)出身
※所属や職位の情報は全て取材時点での内容です。

