トピックス
- スポットライト
- 研究
- 2021
【第4回 インタビュー】 バイオエンジニアリング専攻 安楽泰孝先生
どんな薬でも脳へ送る薬の「運び屋」ナノマシン
―生体バリアを自在にくぐり抜ける体の中の「はやぶさ」を作る!―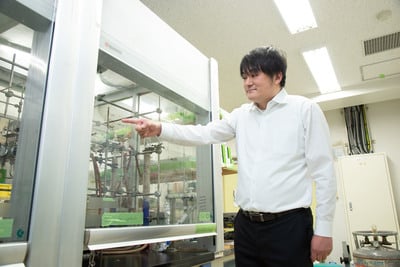
「3秒に1人、新しい患者が発生している」といわれるアルツハイマー型認知症。大きな社会課題である脳の病気の診断・治療に患者の負担の少ない方法を使えたら……。体の中で活躍する極小サイズの「ナノマシン」がそんな世界を拓いてくれます。東京大学大学院工学系研究科・工学部の第一線で活躍する若手研究者の皆さんと、染谷隆夫工学系研究科長が研究の成果と未来、発展のために必要なことについて語り合う対談の第4回。新しい医療につながる研究を分野を越えて融合、発展させるための対話となりました。
ナノ粒子が開く世界
染谷:安楽先生は、100ナノメートル(0.0001ミリメートル)規模という極小サイズの多機能高分子集合体「ナノマシン」というものの研究に大きな夢を持っているとうかがっています。どのような研究なのか、教えてください。
安楽:アルツハイマー病などに代表される脳神経系疾患の治療、診断に役立つ、高分子を使ったナノ粒子を薬剤送達システム(DDS)に展開する研究をしています。私はもともと高分子科学の研究をしていて、中でも、機能や特徴の異なる高分子を用いて調製したナノ粒子が生体内でどのような挙動を示すかといったことに興味を持っていました。
ナノ粒子によるDDSは、たとえばがんの治療に使うことが考えられます。従来は、がんのあるところまで薬を届けて、そこで薬をリリースすることで治療したり、診断していました。最近ではナノマシンを使って、がんに薬を届けるのではなく、がんに製薬工場をつくって、体の中で薬をどんどん作り出すというシステムができるようになってきました。
脳のバリアを越える!
安楽:がんだけでなく、脳への薬の送達という目標もあります。脳への薬を送ることは、がんよりけた違いに難しい課題です。血液から脳へ薬を送り込もうとすると、BBB(血液脳関門)という生体内バリアに阻まれてしまいます。アルツハイマー型認知症などの治療に使われる「ドネペジル」という薬がありますが、これは投与された量の0.1%しか脳に届かないというくらい難しい。最近では「抗体医薬」という病気の原因となっている物質を取り除く薬が注目されていますが、これも0.05%程度しか脳に届きません。脳に薬を運びたいという要望はかなり高いのですが、なかなか実現できていないのが現状です。実は、私たちはすでに脳へ薬を6%ほど運ぶことができるシステムを作り出しています。
染谷:すでに脳の関門を突破されているのですね。それはどのような仕組みでしょうか?
安楽:脳はグルコース(ブドウ糖)を唯一のエネルギー源としています。グルコースはグルコーストランスポーター(GLUT1)により脳内に取り込まれます。このGLUT1は空腹と満腹のときでは局在する場所が違うとされています。空腹の時は血管側にたくさんあり、ご飯を食べて満腹になるとこれが移動するのですね。そこでグルコースを表面につけた「高分子ミセル(ナノマシン)」とGLUT1の生理学的特徴である局在変化を組み合わせます。まずお腹が空いた状態でGLUT1が血管側にたくさん出ているときにナノマシンを投与します。それから食事をさせると、GLUT1の局在変化に伴ってナノマシンが脳の中に持ち込まれていくわけです。生きたマウスの脳を麻酔下で観察すると、脳表面から深部まで、ナノマシンが一様に分布していることが確認できました。
このシステムで、従来の抗体医薬に比べて60倍以上、脳へ薬を届けることができます。実はこのナノマシンの中に抗体を20分子くらい入れることができるので、実際はさらにその20倍になります。先程のアルツハイマー治療薬「ドネペジル」ならば、100~150倍というとんでもない量を運ぶことができるようになります。
ドネペジルはすでに臨床で使われている安全な薬ですが、効果を得るために大量に投与しなければならなかったところ、ナノマシンに搭載することで投与量をかなり下げることができる。この成果は2015年にでていたのですが、学術誌のネイチャー・コミュニケーションズに投稿したところ、査読者になかなか信じてもらえなくて、2017年に掲載されるまで大変でした。
最近ではこのシステムに核酸医薬という薬を実際に乗せる実験を行っています。マウスの迷路通過テストをすると、アルツハイマー病のマウスが病気のないマウスに近い成績を出すことができ、それでいて薬の投与量は10分の1程度という効果を確認できています。
染谷:がんやアルツハイマー病など、すでに社会の中で目標となっている病気に利用できる研究をされているわけですから、すぐにでも社会実装に繋がりそうですね。先生ご自身が企業を起こすということもできそうです。
安楽:はい。私たちはこの技術を広く社会実装をしたいと考えて、ベンチャー企業を作りました。ボストンにも拠点があり、多くの会社とライセンス契約して、波及効果を高くしようと考えています。
脳の中で「はやぶさ」のようにサンプルリターン
染谷:先生の研究成果はすでに社会の中で活躍しつつあるわけですね。将来の展望はどういったものがありますか?
安楽:2年前に第1回の克研究奨励賞をいただいたときに提案した「はやぶさ型ナノマシン」の開発をめざしています。
染谷:小惑星探査機「はやぶさ」は、小惑星に行って表面の物質を採取して地球に戻ってくる、「サンプルリターン」というミッションですね。小惑星探査機がどのように研究のヒントにつながっていったのでしょうか?
安楽:私たちはこれまでは脳やがんに薬などを「届ける」ということを目標に研究を進めてきたのですが、ちょっと視点を変えて脳の中の情報を取ってくるということを考えています。私たちのナノ粒子は、体の中で動的に構造を変化させることができます。また、脳の中にとんでもない量のナノマシンを運ぶことができる。この2つのメリットを活かして、「はやぶさ」のように脳の中で物質を回収し生体内情報を採取して、血流へと戻ってくることができないかと考えたわけです。
染谷:脳から物質を取って戻ってくるとは、まるで魔法のような研究で本当にわくわくします。ただ、「はやぶさ」はエンジンを持っていて宇宙を航行することができますが、ナノマシンは自分で動くことができるわけではないですよね。どのような発想で、「体の中で意図した通りに移動する」という方法を考えられているのでしょうか?
安楽: BBBを越えて脳に薬を届ける、つまり「行く」ということはもともとできていたわけです。さらに、脳の中で物質を取る「サンプリング」という機能までは付与することができました。ここで「血液中に戻ってくる」機能が重要となるのですが、物質によってはBBBを越えても脳内にとどまることができずに再度血流に追い出されるような薬剤もあります。そこで反対にその仕組みを利用して、ナノマシンを血流中に戻ってくるようにできると考えています。
染谷:これまで脳内にとどまることが難しかった薬剤の弱点を、逆転の発想でうまく利用しようというわけですね。
安楽:アルツハイマー病の診断では、これまで丸一日かけて髄液検査するなど、患者さんにとってとても負担の大きい方法をとっていました。「はやぶさ型ナノマシン」を使うことで、血液を回収するだけで診断できて、圧倒的に負担の少ない診断を実現できます。
一冊の本との出会い
染谷:先生がそもそもナノマシンという素晴らしい研究領域に興味をもったのはなにかきっかけがあるのでしょうか?
安楽:私はもともと富山大学の高分子と水の関係性を調べる研究室にいたのですが、研究室に配属されたその日に当時の先生から『ドラッグデリバリーシステム』という本を渡されて、読んでみてDDSという技術のことを知り、「こんなことができるのか!」 とびっくりしました。本を読んだその日から「この研究室に行きたい」と著者のお一人で、この分野をリードされている片岡一則先生の研究室を目指して、博士課程から東大に来たのです。
染谷:本一冊に出会ったことでこの分野に来られた。とても貴重な出会いですよね。そして片岡研究室では、当初のがんの研究から脳の研究を始められている。ターゲットを移動するのも大きな転換だと思うのですが、がんから脳というより難しい方目標へ移ったのはなぜでしょうか?
安楽:実は、私の研究内容はもともとがんを治すというものではなかったのです。片岡先生の研究室には低分子、核酸、抗体といった薬ごとに分かれているグループがありました。私が配属されたグループは、ある特定の薬を運ぶということを目的としておらず、基礎的な高分子科学に基づいた新しいナノ粒子を作ることを目的としていました。このナノ粒子ががんを治すDDSキャリアに使える、ということで共同研究者がさまざまな用途を提案してくれたわけです。とはいえ脳は難しいので、挑戦しようという人が誰もいませんでした。あえて挑戦してみようと思い、脳の研究を始めました。
染谷:新しいことにチャレンジするのは、道具立ても必要ですし時間もかかります。そこで先生はこんなに短期間にどんどん成果を挙げられた。驚くばかりです。
安楽:脳に運ぶということにはもちろん難しさがあるのですが、ある程度はがんを目標にシステムができていたので、完全にゼロからというわけではなくあまりハードルは感じませんでした。抗がん剤や核酸医薬を運ぶ研究をされている先生方もいますし、私はむしろ、核酸も、抗体も、遺伝子も、何でも運べる今までになかった新しい方法論を作ろうと思いました。
東大でなければできないことがある
染谷:先生は基礎学術も卓越していらっしゃいますし、さまざまな境界融合領域を開拓されています。研究を発展させ、分野を融合させることが本当に大事になると思うのですが、そのために研究科への要望はありますか?
安楽:すごくクリティカルなところですと、私は任期満了の後は移動を考えなくてはならないかと思います。それは仕方ないことですが、東大の工学系というのはかなり自由で、ここから移動すると動物実験はできません、というようにできない研究が山のようにあります。そうなると、今考えているアイデアややりたいことができなくなってしまいますね。
染谷:活躍している若手研究者が、大きなチャレンジができるようにポジションを整えるのが私の最優先で重要な課題です。非常に重要な要望だと認識しています。
安楽:それから、研究室の面積は少々厳しいものがあります。他の先生方とスペースを共有しなければならないので、これはかなりきついですね。
染谷:スペース面積についての要望はこれまでにもきていますね。多少は時間がかかりますが、存分に先生が研究できる環境も整えていきたいと思います。
分野を融合して、さらなる発展へ
染谷:先生の研究は、さまざまな薬を脳に届けられる新しいツールを生み出し、非常に大きな前進だと思います。薬そのものではなく、運び方、届け方という研究でより汎用性のあるものを作られた。そこで実用化、波及効果という点に加えて、次なる大きな学術的挑戦はなんでしょうか?
安楽:まさにその点で、他の領域の先生方に相談しようと思っています。「はやぶさ型ナノマシン」を応用して、うつ病に使えないか? ということなのです。うつ病の診断の場合、医師が患者さんの様子を診察して「うつ病か、そうでないか」ということを判断しています。脳に何か挿入して物質を採取するということができない。遺伝的な病気ではないですから、DNAに何か見つかるというわけでもない。うつ病を調べている先生方と一緒に、「はやぶさ型ナノマシン」を使って、脳の中に局在する分子情報に基づく脳機能・疾患の理解をしたいと考えているのです。
将来は、脳の中から何かの物質をとってきて、体に装着したウエラブルデバイスとも融合させ、デバイスに送った情報を体外に発信できて病院に届くということができないかと思っています。そうすることで、医師と患者さんの関係が変わるパラダイムシフトが起こせるのではないでしょうか。今までは、体調が悪くなると患者さんが病院に行くという仕組みでした。それを根本から変えて、情報の方が先に病院に届くので、医師から患者さんに「来てください」という、今までとまったく違った医療を展開できないかと思うのです。私は脳の研究をしているので、まずは脳の健康状態をリアルタイムでずっと監視できるようなシステムができないかと考えます。
染谷:情報を発信するというのは、センサーのようなイメージではなくて、自分で電波を出す、というようなことでしょうか? それならば、ウエアラブルデバイスを研究している私たちの側からインフラを提案できるかもしれません。
安楽:そうした機能を実現するには、どのような情報を発信するとよいと思われますか? 何か特定の波長の電波を発するとよいのでしょうか。
染谷:もっとも単純に考えてよいと思いますよ。何らかの物質が存在するとき、光を当てると波長が変化する、という機能があればよいのではないでしょうか。現在のウエアラブルデバイスというものは、脈拍を光で見ているわけですし、パルスオキシメーターのウエアラブル版も登場していますね。そこで何らかの物質があるかないか、ということを調べる際には、2波長を使えるとより精度よく調べることができます。先生の「はやぶさ型ナノマシン」が戻ってきたとき、目標の物質があるとウエアラブルデバイスが正確にキャッチするということが可能でしょう。
安楽:それでできるのですね。それならば、ある波長の光を当てたときだけ、特定の物質が存在すると光を発するという分子があります。そうした波長が変わる物質を組み込めばよいと思います。
染谷:認知症というのは症状が行動に現れる病気です。現在のチェックシート式の検査では、認知症がかなり進行してからでないと診断できないのですが、全身のモーションキャプチャーシステムによって行動を調べることで、もっと早期に認知症の可能性が高い患者さん群を抽出する技術もあるのではないかと私たちの研究グループは考えています。早期に認知症患者さんに投与すると効果があるけれど、進行してしまうと効きにくくなるような薬があるならば、私たちの早期診断のシステムと、先生の研究を組み合わせると大変面白い、融合して発展していく領域になるかもしれませんね。
安楽:私はさまざまな共同研究者が研究科にいて、壁がなくて自由で研究しやすいと思っています。専攻に限らず、他の分野とも壁を感じずに共同研究ができ、とても自由です。この環境で、脳にどんな薬でも自由に送り届けることができて、しかも脳の中にある情報を自由に取り出せるシステムを開発していきたいですね。
Profile
安楽泰孝准教授
鹿児島市立星峯中学校(鹿児島県)出身、鹿児島県立鹿児島中央高等学校(鹿児島県)出身
聞き手:研究科長 染谷隆夫教授
東京学芸大学附属竹早中学校(東京都)出身、東京学芸大学附属高等学校(東京都)出身
※所属や職位の情報は全て取材時点での内容です。

